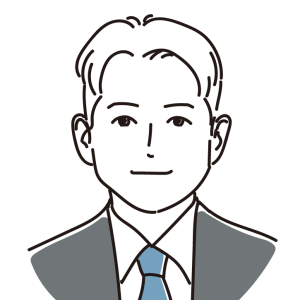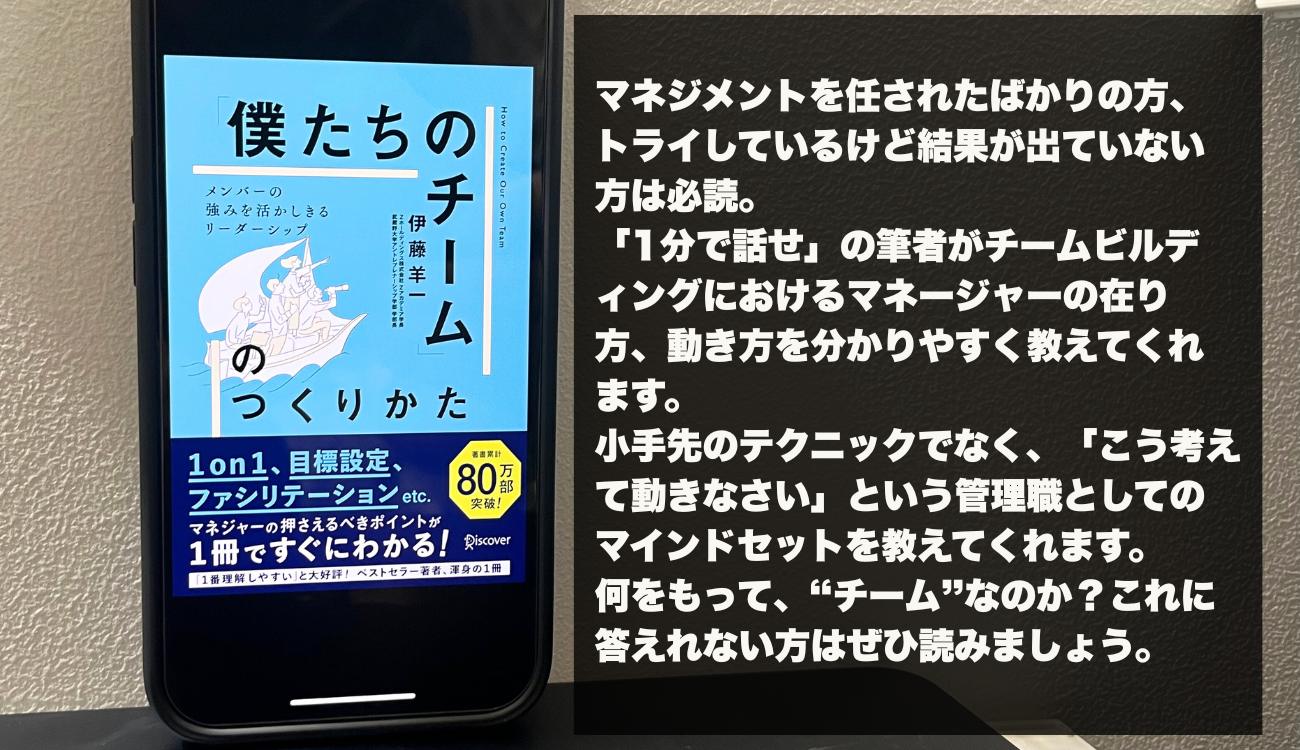
はじめに
今回紹介させていただくのは、ベストセラー「1分で話せ」の筆者 伊藤洋一さんが書かれた「僕たちのチームの作り方 メンバーの強みを活かし切るリーダーシップ」です。
こんな悩みがある方におすすめ
- チームメンバーのモチベーションに温度差がある
- チームのメンバーに自主的に動いてもらうためにはどうしていいかわからない
- 自分一人でリードしていく自信がない
- チームメンバーにやる気を出してもらう方法がわからない
- もっとチームメンバーの強みを引き出したい
本書はメンバー全員がチームのことを(自分事)として捉え、ひとりひとりの強みが発揮され、成果が上がる。
そんなチームを作るためのリーダーシップについて学べます。
小難しいリーダーシップ理論ではなく、シンプルかつ”今、求められているマネージャー象”の核になる部分を学ぶことができました。ポイントを振り返りながら自分なりにまとめてみます。

私は本書をKindle Unlimitedのおかげで無料で読めました。ビジネスの良書が読み放題で学べます。また使ったことがない方はこの機会にぜひ無料体験から試してみてください。
私が読書に使っているおすすめのサービス
Audible(オーディブル)なら、12万作品以上が聴き放題!
▶️🎧聴き放題のAudible(オーディブル)無料体験へ!
⇨30日間の無料体験キャンペーン中
Kindle Unlimitedなら電子書籍が読み放題!
▶️▶️Kindle Unlimitedの無料体験へ!
⇨30日間の無料体験キャンペーン中
audiobook.jpなら、1.5万作品が聴き放題
▶️▶️▶️audiobook.jpの無料体験へ!
⇨2週間の無料体験キャンペーン中
大前提:リーダーになっても、自分の能力向上は必須
本書の中でも触れられていますが、”リーダーシップを身につけるためには個人の能力の向上”が欠かすことができない。

リーダーになった、で終わりではないんですよね。
やらされるのではなく個人としてどう自分を鍛えていくのか
”LEAD THE SELF”=自分自身をリードしていくことが重要。
自分自身の核となるもの
- 自分自身が大事にしていること(過去の経験から生まれたもの)
- 未来の自分に対する想い←どんな形でもいいので、未来の自分の姿を形にする時間をとってみましょう。
自分の想いを持ち、主体的に働こうとすることで、理想の自分になるために知識を身につけ、スキルを鍛え、何事もチャレンジするようになる。
しかしこの本を読む私のようなマネージャーの人間はみんな感じているだろうが、私たちは一人で何か大きなことを成し遂げることはできない。

チームのあり方について本書のスタンスにとても共感しました。
「チームの形」は人それぞれ、チームごとに異なる、常に個別解なのだ。
そしてそれを考えるのは私たち自身だ。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
本書で提示されるのは、一つの尺度に基づく土台。その土台に基づき自分のチームだったらどうなるんだろうと考えるヒント、必要な要素を7つの章に分けて教えてくれるのがこの本です。
マネージャーの定義もすごく気に入っています。
リーダーシップとは、チームをリードする人(Leader)のあり方(ship)だ。
ではマネジメント(management)とは何か?
動詞はmanageだ。
これには「管理する」「経営する」という意味もあるが、「何とか成し遂げる、何とかやっていく」という意味もある。
I can manage the situation(こんな状況なら何とかなる)
マネジメントを「何とかすること」と考えると、マネージャーはmanageする人(er)、(何とかする人」だ。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
ここからは私が本書を読んで実際に役に立ったと思える部分を、自分なりにまとめていきます。
リーダーの最優先事項は「メンバー1人ひとりの強みを活かしきること」
この記事を読んでいる人は「マネジメントに悩みがある方、興味がある方」だと思います。
あなたのチームは、チームの目標がチームメンバー1人ひとりの中で消化され、(自分は今季、何を実現しなければいけないか)をみんなが明確に認識しているでしょうか?

主要な数字がおぼつかないスタッフもいるかも、、、
もしくは、チームメンバー同士の人間関係に問題を抱えていることはないでしょうか、
1人ひとり違う人間が集まってチームになっているから、合う人間も合わない人間もいる。
毎日同じチームの中で仕事をしていると、性格や主張のちょっとしたズレが大きく広がっていき、いつの間にか(あの人と一緒に仕事ができない!」」という状態になっていたりする。いろんな職場で見てきました。
あるいは、チームメンバーのモチベーションに温度差があり、ポジティブにガンガン頑張るぜ!というメンバーも多いが、ネガティブでやる気がない(そのように見える)メンバーが全体の空気を壊して困っている、ということはないでしょうか。

対話しても、こんな人が多いよ。
- やる気を見せず、(別に)と斜に構えた反応をする
- 表向きの返事は良いけれど、行動が伴わなかったり、裏で愚痴を言ったりする
- 言い訳が多くて、改善する気がない
そんな人たちはどこにでもいますね

チームの多くがポジティブなメンバーだったとしても、このネガティブでやる気がないメンバーが少し交じるだけで、チームの士気は大いに下がってしまうことになる。
結果として、チームリーダーは「ネガティブメンバー対策」に追われ、全体像が見えなくなったりする。
あなたはなぜそのメンバーがネガティブになっているか、その背景や要因に気づけているだろうか?
反対に、(自分のスキルを上げていき、チームに貢献したい!)というメンバーもいるだろう。
そういうメンバーのやる気はうれしいものだ。ただ、そのメンバーのスキルが上がるように的確にサポートできているだろうか?改めて申し上げるならば、それらの課題に向き合うことはすべて「リーダーの仕事」だ。
これらを解決せずして、リーダーシップもマネジメントもない。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
メンバー1人ひとりに向き合う。エネルギーが必要ですが、リーダーをするうえで避けて通れないことなのだ、とわかりました。
向き合う努力がないと相手の求めているもの、状態、心理状態への理解は深まることがないのです。
でも実際、そういった場面を乗り切る時リーダーである自分には何が必要なのでしょうか??傾聴するスキル?忍耐力?
本書で学べるのはそういったものとは全く違う二つのことです。
”チームの問題”を乗り越えるためのリーダーに必要な2大ポイント

本書の中では、大きく下記の二つが必要を説かれています
- 志
- チームをゴールに導くアクション
順番に見ていきましょう。
リーダーに必要なポイント ①志

志とはなにか?
一言で言えば「自分は何を成し遂げたいか」という想いです。
あなたはなぜ今の会社にいるのでしょうか?
「今の会社や組織に、なぜ自分は参加しているのか?』ということです。
ここで大事なのは冒頭でも書かれていた、
”LEAD THE SELF”=自分自身をリードしていくこと。リーダーならば、自分がそこにいる理由を受け身で考えるのではなく、主体的にとらえ行動しましょう。
わかりやすいですよね、”何で自分はこの仕事をしているのか?”その答えってすぐに答えられる人は意外と少ないと感じます。
次は志をもつことで得られる3つのメリットをみていきましょう
志を持つべき3つの理由 志を持つことで、主体性を発揮できる
リーダーはチームをリードする。もちろん、全部好き勝手できるわけではないです。

会社の指示を聞かないわけにはいかないよ
それはそうでしょう。会社人である限り、会社全体のミッションやビジョン、そして事業計画を無視しては、チームをリードすることはできません。
ですがその中でリーダーには主体性が求められるのです。
例えば自分たちの方針と会社の方針が違う時があるでしょう、そんな時私たちはリーダーとしてメンバーにどう伝えたらいいのでしょうか

僕も(みんなと同様)反対なんだけど。上がやれって言うからさ〜
と言ったらどうなるでしょうか
自分がメンバーだったらどう思いますか?
私だったらドン引きですね
「いやいやリーダーのお前に意志はないのかよ』と感じるでしょうね。
そういう場合でもたくさん考え抜いて自分なりに意思を持つ、ことが重要なのです。
例えば私は小売業をしているので、「やりたくないけど、会社の指示でやらないといけないもの」はセールですね。
自分がメンバーに伝えるなら下記のような感じでしょうか。

値引きはしたくないけれど、会社全体の運営資金を確保するためのアクションとしてやらざるを得ない。
値段を下げることで新規顧客の間口が広がるから、次につながるお客様を獲得できるようにセール品を売るだけで終わらせず定番、新作も絡めて提案することを徹底しよう。安く買える、だけでなく「ここに来たら素敵な提案をしてもらえる」と思って帰ってもらおう。
接客機会も増えるし、自分のスキルを磨くチャンスにしよう。
各業界で直面する問題や課題はことなるのでしょうが、いかに”自分はこうしたい”をチームに伝播させていくか、が大切なのだなと捉えました。
大切なのは表現の問題ではない。リーダーとしての「志」に照らして、あらゆる事象を考え主体的なスタンスにしていこうということだ。
中略
リーダーの主体性は、メンバーを動かす。そしてリーダーが主体的になるために自分はどうしたいかという「志」を持つことだ。
引用元:引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
志を持つべき3つの理由 志が、明確な判断基準になる
リーダー自身としても、意思決定する際に判断が明快になります。
その志に当てはめて、すべてのことを判断できるようになるからです。
このパートを読んで思い出したのは、昔の上司にも言われた一言。「その対応はお客様にとってスマートですか?」
今振り返ると、その上司はなにかあるごとに判断の基準がお客様にとってスマートかどうか?を指示や判断の基準にしていたように感じました。
志に基づく判断を積み重ねていくと、志の実現に近づく。一つ一つの意思決定に、悩まなくなっていく。軸が明確だから、後悔も少なくなる。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
志を持つべき3つの理由 仕事が楽しくなる

これはそうだろう、と思いました。自分の中で主体性ができると意思決定にブレなくなり、前進している感覚が強くなりますよね。
補足:志の育て方
「志」を育てる方法として本書が提唱するのは「振り返り」です。
人生を振り返り、自分が何に心を躍らせ、何をつらいと感じたかを思い出すことで、自分の原点や方向性が見えてきます。
さらに、日々の仕事の中で「なぜ嬉しかったのか」「なぜつらかったのか」と振り返る習慣を続けることで、自分が本当にやりたいことが浮かび上がってくるのです。
実行と振り返りを繰り返すサイクルを回すうちに、自分の思い・軸・志が徐々に明確になっていきます。
リーダーに必要なポイント ②チームをゴールに導くアクション
自分の中で志という自身の想いを育むと同時に、リーダーである私たちはチームメンバーに対して具体的なアクションで働きかけていかなければいけない。

このパートを読んで、「やっぱりそうだよねー、わかってはいるんだけどねえ」となりました。
どうすればいいんでしょうか?
冒頭にあった通りリーダーの役割とは、チームをゴールに導くこと。
一人で実現するのではない。その仕組みや環境を作り、日々の働きかけを行ないながらチームメンバーのモチベーションを上げ、チーム一丸となり実現して行く。
3つの要素があります
チームをゴールに導くアクション ”ゴール設定”
チームには必ず共通のゴールがある。まずはメンバー全員がゴールを共有することがスタートです。
チームをゴールに導くアクション ”導く”
メンバーの進捗を聞きながら、鼓舞し続けながら、時にはやり方を変えながら、ゴールに向かうプロセスをリードし続ける。
”チームをゴールに導くアクション ”チームにする
ゴールとプロセスだけ提示されても、人は疲弊していく。目標に向かって、それぞれが勝手に動くだけでは進捗のプロセスが回らない。
メンバーが成長し、チームとして目標に向かって進んでいく環境を作るのがリーダーの仕事です。

上記の3つに働きかけ、目的を達成する。そのためにやれることを全部やり、なんとかするのです。
リーダーの役割はファシリテーター
フラットなチームにおけるリーダーの役割とは何でしょう。大事なのはメンバー1人ひとりが成果を出すべくサポートすることです。
以下のパートにはとても共感しました。その人が成果を出すべく相手が何を求めているのかを考えることで、相手にとっての潤滑油のように動くことができるようになった経験があるからです。
リーダーは「指導者」である必要はない。僕は、自身のリーダーとしての役割を「ファシリテーター」だと考えている。チーム全体を引っ張って「指導して行く」のではなく、会議や1on1ミーティングでメンバー1人ひとりの想いを引き出し、何に心躍るかを感じ取ってもらい、本人が成長するサポートをしていく。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
チームの力を最大化する2つのポイント ①環境づくり
いわゆる心理的安全性のある職場=メンバーにとって安全・安心な環境を作ることです。
心理的安全性を確保するには二つのポイントがあります。
- 来たくなる場所にすること
- 言いたいことが言い合えること ←コレ、大事
1番目はもう大前提すぎる感じがしましたが、2番目の「言いたいことが言い合える」というのは、お互いの欠点や弱みを攻め合うような職場であっていいということではないです。
また無礼な態度や馴れ合いを許容することでもありません。

そんな職場では、心的安全性は確保されるわけはないのです
まずはメンバーそれぞれがお互いにリスペクトしている場所を目指すことが重要です。
尊敬しているというほどではなくて互いに存在を認めている状態にすることを目指しましょう。

互いに存在を認めている、という表現が気に入りました。
考えていることは一人一人違う、だから一人ひとりに向き合い聴くことが肝要です。
チームの力を最大化する2つのポイント ②チームメンバー1人ひとりの才能と情熱を解き放つ
上記の「安心・安全な職場」ができたら次は「チームメンバー1人ひとりの才能と情熱を解き放つ」ことを目指します。
メンバーには必ず、元々持っている才能がある。個人個人で差はあるかもしれないが、何かしら、その人なりの強みは必ずある。
そして情熱も同様だ。
情熱を表に出しているメンバーもいれば、おとなしく目立たないが、よく話を聞いてみると、仕事に強い情熱を持っているメンバーもいる。引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
それはそうか、メンバー個人個人で強みが違うし、情熱を前に出さない人もいますもんね。

本書を読んで改めて感じたのは、マネージャーはメンバー1人ひとりに対して「なにか困っていることはないのか、仕事の進捗はどうなのか』など細やかなケアが求められているということ。
チーム全体に働きかけながら、同時に一人ひとりに働きかけなければいけない!
チームがゴールに向かうためにできることは全部やろう。
ただし、なんでもやってあげるのではなくメンバーが自分で解決するためにガイドすることが大切です。
メンバーに自分の課題を言語化し、認識してもらうことも大切ですね。

1on1ミーティングの基本
対話の基本は1on1。まずは定義をおさえましょう。
1on1の定義
「マネージャーがメンバーのために定期的に時間を割き、メンバーの話に耳を傾けることをとうして、目標達成と成長支援する場」
もう少し細かくみてましょう。本書ではポイントは大きく2つです。
リーダーがメンバーのために、定期的に時間を割く
1on1ミーティングは、メンバーのための時間。つまりメンバーが話したいことをテーマにするし、メンバーを理解するための時間でもあるし、メンバーをサポートする時間でもある。

会話の主役はメンバー、ということはすごく大切なポイントですね。
※注意点※
メンバーの自主性だけに任せていると、次第に面倒になって1on1をやろうとしなくなることもある。なので「したい時にする)」では効果は半減してしまうともあります。
これは容易に想像がつく、なのでお互いに話し合って定期的に1on1の時間を設定することが望ましいんだな。
できれば毎週、2週間に一度など、事前のスケジューリングによって、時間を確保しておくほうがいいでしょうね。

メンバーの話に耳を傾ける
上記にもあるように1on1の時間はメンバーのための時間です。
なのでリーダーが話すのではなく、基本はメンバーが話し、リーダーが聞く、ということです。
なぜたくさん話してもらうのでしょうか。
マネージャー側にもメリットがあります。メンバーの状況が分かり、相手に対する理解が深まり、サポートしやすくなりますよね。
そして1番のメリットは
口に出して話をしてもらうことで、メンバー自身の思考が構造化されていく=具体的な形になって行く点です。
メンバーはたくさんの(もやもや)を抱えている。「もやもや)は、何が課題かわからず、なぜこうなっているかを明確にならず、そしてどうしたらいいか分からないから(もやもや)なのだ。
ただ(まずいな!)(わからないな、、、、)という感情がたくさん、まとまりなく、オタマジャクシのように頭の中を蠢いている。という感じと言えばわかりやすいだろうか。
これを言い換えると「モヤモヤ悩んでいる」ということだ。
中略
おたまじゃくしがうごめいている頭の中だけで悩んでいても整理されない。だから、口に出して話していくのだ。相手(リーダー)と話す中で。おたまじゃくしがまとまった主張になっていく、そう簡単にはまとまらないかもしれないが、人に理解してもらおうと話す中で、何を話して、何を離さないで、という取捨選択により、最初の整理がなされる
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一
自分のチームのゴールの決め方

この記事を読んでいるあなたのチームのゴールはなんでしょう。
私のチームのゴールはまず会社が設定した予算をクリアすること、、、だと思うのですがチームというのはゴールを目指しているからチームであるという本書の考え方からするとどうだろう。個人のメリットの結果、一緒に行動しているだけのような、、、などなど
本書を読みながら、何度も考えるきっかけをもらいました。
ここからはどうすればチームの目的が明確になり、一人ひとりに浸透するのか?をまとめていきます。
ミッションとビジョンを決める
ミッション=自分達のチームの使命、役割だ。このチームはなんのために存在しているかの理由。何に心躍るのか、何のためにガンガン働けるのか?
ビジョン=ミッションに基づき行動した結果、実現すべき未来の姿。
未来の姿をビジュアル(Visual)でイメージしたもの
ミッションに基づいて行動し、ビジョンを叶えていく。
⭐︎自分達のチームのミッションってどう決めたらいいんだろうか?
ビジョン=チームのゴールをどう設定するのか?
一組織に属しているのなら、会社全体のゴールが前提となる

自分は、メンバーは会社のゴールを知っているのか??
会社が目指すゴールを踏まえつつ、我がチームはどういうゴールを目指すかを考える。
会社が目指すゴールは無視できないし、それと全く整合性がつかないゴールは目指すべきではない。会社が目指すゴールを満たしつつ、自分達がスペシャルに目指すべきゴールはなんなのか?をチームで議論する。(難しければ、まずは自分の中で納得ができるものを出してみましょう)
ゴールは長期ゴール、中期ゴール、短期の3つで考える。
長期ゴール:いわゆるチームのビジョン。仕事をする際に目指すべき「北極星」
会社、チームの全員が賛成できるものを長期ゴールとする。
注意点!長期ゴールだけを定めても、自分達は具体的にどの目標に向かって進んでいったらいいかわからない。となります。
中期ゴール:確実に達成したい目標に設定する
今いるメンバーで達成したいものであれば、最長でも5年、もしくは3年程度で実現したいことを中期ゴールにすると良いのです。

メンバーの入れ替わりが激しいので、長期ゴールの共有は難しいな、と感じました。その一方で短期ゴールの考え方がとても参考になったのでそのまま引用します。
北極星(長期ゴール)を目指し、登るべき山(中期ゴール)を登頂する。
そのための第一歩は「どこからアプローチし、どこまでひとまず登るか」というステップが短期ゴールだ。
これは年度計画に近いものだと思えばよい。だからいわば「山を登るための登山道」というイメージになろうか。
必ずしもルートが繋がらない中期ゴールと長期ゴールの差と違い、「短期ゴールを実現して、その次のステップはこうして、さらにこういうステップを辿ると中期ゴールの登頂に着く」と明確につながっていると良い。
引用元:僕たちのチームの作り方 筆者 伊藤洋一

私自身がチームに向けて提案するならこんな感じかな、
長期ゴール:Aグループに入る。エリアの1番になる
中期ゴール:全員が10万円のインセンティブを平均して稼げる店にする
短期ゴール:毎月予算を取れる店にする
まとめ
最後に私が感じた本書のキモをまとめます。
- リーダーは、メンバーを生かすのが仕事
- そのために、フラットの場を作る
- そして、メンバーの思いや考えを聞く
- 会議の場でもフラットに意見を出し合う
- チームはゴールを共有しているからチームなのだ
- 踏み出し、続けることが大事
繰り返しになりますが、本書で伝えられているのは
リーダーの仕事とは?
「メンバー1人ひとりにフラットに向き合い、寄り添う」スタンス。大切なのはスキルではなくマネージャーとしてのマインドセット。
マネジメントを任せれたけれど上手く結果が出せずに悩んでいる方、もっと成長したいと思っている方はぜひ、読んでみてください。
小手先のスキルではなく、自分の中の行動指針が固まるきっかけになるかもしれませんよ。

私は本書をKindle Unlimitedのおかげで無料で読めました。ビジネスの良書が読み放題で学べます。また使ったことがない方はこの機会にぜひ無料体験から試してみてください。
私が読書に使っているおすすめのサービス
Audible(オーディブル)なら、12万作品以上が聴き放題!
▶️🎧聴き放題のAudible(オーディブル)無料体験へ!
⇨30日間の無料体験キャンペーン中
Kindle Unlimitedなら電子書籍が読み放題!
▶️▶️Kindle Unlimitedの無料体験へ!
⇨30日間の無料体験キャンペーン中
audiobook.jpなら、1.5万作品が聴き放題
▶️▶️▶️audiobook.jpの無料体験へ!
⇨2週間の無料体験キャンペーン中